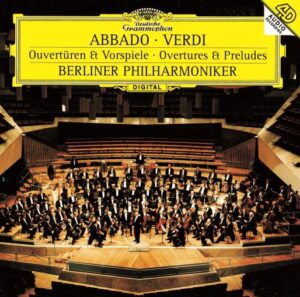~第1回「暗闇の音楽、暗闇の絵画~神聖なるものと人間的なるもの」~

ナイジェル・ショート指揮テネブレ(声楽アンサンブル)
ジュリア・ロイド&グレイス・デイヴィッドソン(ソプラノ)
SIGNUM PSIGCD622 輸入盤国内仕様日本語解説付き
音楽と絵画を関連付けてCDをご紹介する企画「音楽は絵画のように」。今回ご紹介するのは、キリスト教の聖週間の真夜中に行われる「朝課」という蝋燭の灯りのみという薄暗闇の中で行われる典礼で歌われていたクープランの「ルソン・ド・テネブル」とジェズアルドの「レスポンソリウム」を収録したー枚です。どちらも同じ聖週間に歌われる音楽でありながら、全く性質の異なる作品をカップリングしている画期的なCDです。フランス・バロックのクープラン、イタリア後期ルネサンスのジェズアルド、と時代も国も異なっていますが、その作風の違いはそうした相違以上で、正反対とも言えるものです。それではCDの内容を見ていきましょう。

華麗な装飾で彩られたクラヴサン(チェンバロ)音楽で有名なフランス・バロックの巨匠フランソワ・クープラン。鍵盤音楽史に名を残す彼は、クラヴサン音楽に知名度は劣るものの、小規模な編成の教会音楽も残しています。その代表作と言えるのが『ルソン・ド・テネブル』。暗闇の朗読(またはお務め)という意味で、聖週間の真夜中に薄暗い礼拝堂や教会で歌われていました。テキストには旧約聖書の、いわゆる「エレミアの哀歌」が使用され、新バビロニアによって徹底的に破壊され、荒廃した聖都エルサレムへの嘆きが切々と歌われます。クープランの音楽は三部構成という比較的大きな規模を持ちながら、独唱と重唱、そして通奏低音のみという大変小さな編成で書かれ、その旋律も極めてシンプルながら大変美しく、気品がありながらも親しみやすい音楽となっています。きらめくようなまばゆい装飾が特徴のクラヴサン音楽とは一線を画すものですが、どちらもクープランの音楽のすばらしさを伝える側面でしょう。典礼が進むに従って、徐々に蝋燭の灯りを消していくというこの典礼の暗闇の中で歌われるこの音楽は、そうした演出があることによってさらに心に染み入るものになるのでしょう。教会音楽というと、どうしても厳かでどこか近寄りがたいイメージがあるかもしれませんが、この音楽は誰もが親しみを持ちやすいあたたかみのある雰囲気を持っています。それでも俗っぽさのかけらも感じさせない清廉で敬虔な音楽になっているところが、この作品を稀有なものにしている理由かもしれません。

ワシントン・ナショナル・ギャラリー
さて、キリスト教の信仰を持っていなくても虜にしてしまう魅力を持つこのクープランの『ルソン・ド・テネブル』のイメージを、視覚で表すような絵画が存在します。それがジョルジュ・ド・ラ・トゥールの『マグダラのマリア』です。
ラ・トゥールは17世紀フランスの画家で、ルイ13世の宮廷画家にもなったという当時は著名な存在でしたが、その後忘れられ、20世紀も後半になって徐々に再評価されはじめました。その作風から「夜の画家」という愛称が付けられ、21世紀には人気の画家になっていきました。国立西洋美術館にも、近年彼の真作『聖トマス』が収蔵され、日本でも大規模な展覧会が開催されるなど、その知名度も上がっています。ラ・トゥールの絵画の特徴である暗闇の表現と、我々の近くにもいそうなありふれた市井の人間像を組み合わせた作風は、親しみやすく、かつ印象に残るものです。ここに掲げた絵画は、マグダラのマリアを描いた作品です。マグダラのマリアは自らの行いを深く悔い改めて、イエスに従ったキリスト教の聖人ですが、ラ・トゥールの絵画の中の彼女は、蝋燭の灯だけが光源となる暗闇の中、左手を頭蓋骨にかけ、右手で頬杖をついて物思いに沈む若い女性として描かれています。自らの過去の行いを思い返し、懺悔している。そんな場面を描いているのですが、彼女がマグダラのマリアであることを示す道具や持物(西洋絵画の用語で「アトリビュート」と言います)がほとんど描かれていないシンプルな画面のため、普通の女性がなにやら物思いにふけっているように見えますよね。ここにいるのは威厳のある聖人ではなく、どこにでもいそうな、ごく一般的な若い女性なのです。静謐で敬虔な雰囲気があるのに、どこか我々の近くに寄り添ってくれそうな親しみやすさを持っています。こうした特徴から、キリスト教の信仰の有無を問わず、魅力を感じる絵画になっているのです。宗教的作品なのに、世俗の要素が強い。けれど卑俗にならず、神聖さや敬虔ささえ生んでいる。この特徴はそのままクープランの『ルソン・ド・テネブル』にも当てはまります。そういえば、『ルソン・ド・テネブル』は蝋燭の灯のみの暗闇の中で歌われます。まるであつらえたようにぴったりな音楽と絵画ですね。

メトロポリタン美術館
ラ・トゥールは「悔悛するマグダラのマリア」という同じテーマでたくさんの絵画を描いています。例えば、有名な絵画としてはメトロポリタン美術館にある作品(上掲)です。こちらもワシントンの作品と同じく、暗闇の中で蝋燭の灯だけが光源となっています。同じように鏡が描かれていますが、鏡は虚飾の象徴です。蝋燭の灯だけの暗闇で、マグダラのマリアは、派手に着飾っていた自分の過去を省みているのです。こちらもごく普通の素朴な女性を、聖なる存在として描いています。ここでも、聖なるものと俗なるものの融合がなされています。ラ・トゥールはこうしたタイプの「マグダラのマリア」を幾枚も描きました。現存するだけでもけっこうな枚数になりますので、当時から人気があり、需要も多かったのでしょう。聖なる存在ながら親しみやすい。だからといって卑俗にならない。その絶妙なバランスが保たれているラ・トゥールの「マグダラのマリア」は、彼にとっての大ヒットシリーズでした。
さて、こうした経験で、かつ親しみやすい宗教絵画を描いたラ・トゥールですので、さぞかし信仰心に篤い敬虔な人物だったのだろうと考えてしまうのですが、実情はどうやら違ったようです。彼は、出世欲が激しく(後に貴族になっています)、お金にがめつく、それが原因でもめ事も起こしていたといいます。マグダラのマリアを描いた絵画からは考えらえない、なんとも俗っぽい人柄だったのです。我々はどうしても描かれた絵画からその画家の人間性を推し量ってしまいますが、ラ・トゥールという画家は、描いた絵画と人間性が一致するわけではない、ということを教えてくれる格好の材料となっているのです。

次はCDに収録されたもう一つの作品、ジェズアルドの「レスポンソリウム」に話題を移しましょう。レスポンソリウムは英語のresponseの語源となったラテン語で、キリスト教典礼では、答唱または応唱と呼ばれています。エレミアの哀歌に呼応し、セットで典礼の中で歌われます。ジェズアルド以外にも、ビクトリアやゼレンカなどの名作が残されています。エレミアの哀歌のテキストを持つ「ルソン・ド・テネブル」に対応するのが、レスポンソリウムなのですから、このCDの組み合わせ方は、そこだけ見れば至極当然なのですが、あまりにも両者の作風が異なるので、特異なものとなっているのです。
ジェズアルドはルネサンス時代後期の貴族でした。ヴェノーザという公国の君主であり、作曲家でもありました。いわゆる職業作曲家ではないことが、彼の作風を自由なものにしたのかもしれません。彼の作風は激しい情念表現を持つもので、当時は禁忌とされていた半音階進行や不協和音を大胆に使用しています。もちろん半音階進行や不協和音は他の作曲家も使用していましたが、あくまで曲の一部としてでした。ジェズアルドの場合はそれが音楽の主要素となっている点が特異なのです。また転調の用い方も独特で、当時の音楽書法からは逸脱するものでした。こうした彼の特徴は、彼が職業作曲家ではなく、音楽で食べていかなくても済む高い身分だったからこそ、当時の約束事にとらわれない大胆な表現ができたという面もあるのですが、それ以上に彼の鬱屈とした性格が影響しているように思えます。不倫をしていた妻の不貞の現場を押さえ、一緒に連れて行った衛兵に殺させたというエピソードは、ジェズアルドの最も有名なものです。嫡男が早死したことで、急に家督を次ぐこととなってしまったジェズアルドは、生来内向的で自らの世界に閉じこもりがちだったので君主には向かない性格でした。それが不貞の妻の殺害の報復を恐れ、そして人の手で殺させたことで周りの貴族たちから非難を浴びるという現実から逃避するために田舎の城にこもって作曲に明け暮れたそうです。妻の不倫が公になってしまったことで立場上、手をかけざるを得なくなってしまったのですが、そうであっても自らの手を汚すことは彼の性格上できなかったのでしょう。第三者の手による妻の殺害という罪を負った彼を慰めたのは音楽ですが、彼の生み出す音楽は、そこに罪の意識や死の影を感じさせるものが多く、非常にドロドロとした人間の内面をえぐり出すような凄まじい音楽になっています。クープランの清浄な世界とは完全に異なる、人の血にまみれた感情渦巻く世界です。ジェズアルドの音楽の特徴を最も表しているのは世俗音楽であるマドリガーレですが、この「テネブレ・レスポンソリウム」という教会音楽においても、それは感じられます。不協和音や半音階進行、一般的な作法からはあり得ない唐突な転調を駆使し、不穏な雰囲気の中で人間のドロドロした感情をもって神への祈りを高らかに歌うこれらの作品は、同時代に書かれた他の教会音楽とは完全に一線を画します。この蠢く情念表現を、天上的な美しさや調和が重んじられる教会音楽にまで用いたことは驚きを禁じえません。ジェズアルドという作曲家ならではと言える個性です。

さて、ジェズアルドとよく関連付けられる画家が、ほぼ同時代のカラヴァッジョです。近年、日本でも大人気の画家となっていて、日本語での書籍もたくさん出版されていますので、ここでは詳しくは記しませんが、人々の心に強烈に焼き付く彼の絵画は、存命当時から多くの追随者を生み、その後の絵画史に多大な影響を及ぼしました。生来、気性の激しい彼は、日常的にトラブルばかり犯しており、ついには殺人にまで至ってしまいます。追手を逃れ、遍歴する中で、日差しが降り注ぐ真夏の海岸で行き倒れるという最期を迎えたカラヴァッジョに、気が休まる時はあったのでしょうか。彼もまたジェズアルド同じように、罪の意識や自らの抗えない激情に苛まれていました。かと言って彼の絵画は 激情に任せて即興的に描かれたものではなく、意外なほど緻密で練られた計画性のある絵画であることが多いのですが、その中でも彼の激情は表現されました。鑑賞していて痛々しいほどの描写力は当時も賛否両論でしたが、特に同業者である画家たちへのインパクトが強かったからこそ、多くの追随者を生み、時代を超えて影響を与え続けたのでしょう。それでは、カラヴァッジョのマグダラのマリアを見てみましょう。
ラ・トゥールと同じく、こちらも市井の女性をモデルにしているようです。彼女が聖人であることを示す持物は描かれていません。ラ・トゥールの女性と同じように簡素な服装ながら、カラヴァッジョは、胸元を無防備にもはだけさせた、乱れた服装で女性を描いています。これはマグダラのマリアが娼婦であったという過去を想起させるものです。恍惚の表情を浮かべるマグダラのマリアは、神の存在を感知した“法悦”という状態であるのですが、どうにも性的なイメージを与えます。逆説的にこうした間違えを犯した人間でも、悔い改めれば赦されるというメッセージだと見ることもできます。当時、娼婦に身をやつしていた女性たちがこの絵画を見たらどう感じたでしょうか。私たちにも救いの道が残されていると、希望を与えられたのではないでしょうか。カラヴァッジョはその圧倒的な実力から貴族に庇護されることも多かったのですが、自らもゴロツキのような生活を送っていたことから、市井の人々へのシンパシーを忘れたことはなかったようです。このある意味露骨な表情、表現がされているマグダラのマリアの絵画には、カラヴァッジョの、日々を懸命に生きる市井の人々への同情心あふれる優しい眼差しがあるのではないでしょうか。このマグダラのマリアは、同種の絵画がいくつも残されています。カラヴァッジョの真作だけでなく、模写や贋作に近いものまで出てきています。これはこの絵画が当時のから人気があり、需要があった証拠でしょう。絵画的な価値はもちろんのこと、巷の人々に救いや希望のみ道を与えたものでもあったからこそ人気があったのかもしれません。ジェズアルドの教会音楽と同じく、世俗にまみれた作品ながらそこには極めて人間的な心からの強い祈りが込められているのです。

ドーリア・パンフィーリ美術館
ラ・トゥールはカラヴァッジョの影響を受け、特にキアロスクーロと呼ばれる明暗法を自らの絵画に取り入れました。暗闇の中で人間や静物が浮かび上がる特徴的な表現法です。また、画法や表現方法だけでなく、同じような題材を選択することも多かったようで、マグダラのマリアもその例です。ですが、ラ・トゥールの作品の雰囲気と、カラヴァッジョの作品の雰囲気の違いは明白です。ラ・トゥールの作品は、カラヴァッジョの影響下で描かれていながら、この違いには驚きますね(ただカラヴァッジョは、上掲のドーリア・パンフィーリ美術館所蔵の艶めかしい表現が抑えられたマグダラのマリアも描いています。市井の女性を描いたような表現ですし、ラ・トゥールの源泉はこちらのイメージに近い作品だったのかもしれません)。
クープランやラ・トゥールの作品は心を穏やかに、安らかにしてくれます。一方、ジェズアルドやカラヴァッジョの作品は心をざわつかせ、かき乱します。こんなにも異なる作風ながら、それでもそこに込められたものは、同じように神への祈りなのです。

最後にこのCDについて触れておきましょう。イギリスの声楽アンサンブルの中でも世界で最も評価されているグループの一つであるテネブレによる歌唱です。テネブレというグループ名は、まさにこの典礼から取られているわけですが、今回の挑戦的なプログラムは、ソリストとしても活躍する実力派歌手が参加しているこのグループならではと言えるでしょう。クープランの作品では、テネブレが誇る二人の実力派ソプラノ、ジュリア・ドイルとグレイス・デイヴィッドソンが、その美声を活かした清らかで澄んだ歌唱を聴かせてくれます。当時の歌唱形式にそって、ラテン語の歌詞はフランス語発音され、美しい歌唱を柔らかに彩っています。心が洗われるとはこういう歌唱のことなのでしょう。クープランの音楽が持つ厳かで親しみやすいという、矛盾する特徴を最大限表した心に染み入る歌唱で、オルガンとヴィオラ・ダ・ガンバのみのシンプルな通奏低音もその雰囲気に優しく寄り添っています。ルソン・ド・テネブルには数多くの録音がありますが、それらの中でも美しさにおいて群を抜く歌唱と言い切って過言はないでしょう。また、ジェズアルドのテネブレ・レスポンソリウムは、3つのセットがある中で、聖木曜日のセットが選ばれています。前述のようにもともと、ルソン・ド・テネブルの歌詞として歌われるエレミアの哀歌に対応する歌詞を持つ音楽がレスポンソリウムであるので、CDの前半に収録されているクープランの音楽に応える音楽としてプログラムされています。それにしても続けて聴くことによって、クープラン作品との世界の違いは衝撃的なほど明らかになります。各パート一人の小編成によるテネブレの歌唱は、精緻なハーモニーを基本としながらも言葉を表現する時は、表現に徹しています。このスタイルが統一された歌唱により不協和音も際立ち、音楽史的にも唯一無二のジェズアルドの音楽表現が炸裂し、聴き手の耳に、頭に響き渡ります。心がかき乱されるとはこういうことなのでしょう。同じ教会音楽でも、全く異なるアプローチを見せる2つの作品を並べることで、人間の根源的な神への祈りを表現しているかのようにも思えます。親和性を持つ音楽と絵画の全く異なる二つの例。音楽と絵画を一緒に鑑賞することで、このアルバムに対する理解もより深まるのではないでしょうか。このCDを聴くときは、ラ・トゥールやカラヴァッジョの絵画を頭に入れて、部屋を真っ暗にしてその世界に浸ってみることをお薦めします。それは、とても得がたい芸術体験になるはずです。